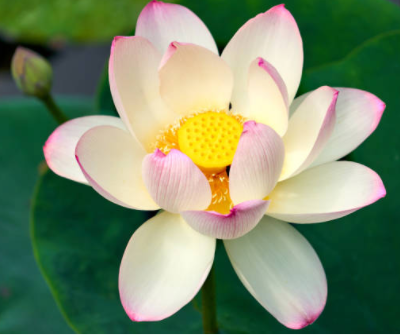成功や実力者に、必要な物事を考察していると何が必要なのか?と思う。
良く日本では、「人」「もの」「金」と、さらに「情報」特に「情報」が必要とされたが、現在更に更新されるなら何が必要なのか。
フォーカスする部分を絞ったお話になるがものはいつも考えようなのだろう。
経営に必要なあなただけの三種の神器には何が大切なのだろうか。三種とは言わず必要なものをピックアップするなら何種あるだろか?
また、人生において大切にしている神器は何だろうか。大切にしている物事、また思考や意思によってすべてに影響を与える「人生の柱」なのだろう。
そう「影響を与える柱」なのだ。
経営資源だけを揃えるなら、「社会的貢献」など特に企業価値が著しく評価される時代になって来ていることで、活動がどう評価されるか、また違った一面も見受けられる時代になってきたりと環境変化に特化した取り組みもスキルとして提案していけるベースになるのだろう。
また、企業の成功にはいつも「人」が、有力な資源と思うのだがどうだろうか?
何故なら成功背景を、外野側から見ていると、外野側の知識や経験で解釈出来るように、見せられているとすれば、世の中の成功者の背景には、何千倍の未知数な他ならない準備と計画があって行われて来たのだといつも思えるのだ。
その多大なる要因の中に重要なポイントが存在している。
そこには、表だった成功者に必要な存在がいつもいる事なのだ。
例えばアップルは、マイクロソフトやグーグルと違い、基本的にハードウェアの会社だ。
創業者で世界的成功者として、スティーブ・ジョブズが有名だが、その右腕として、スティーブ・ウォズニアックと言う人物がいること。
ウォズニアックはハードウェアの天才だが、ジョブズ自体はそうでは無かったのだ。
この「タッグ」の背景には、ジョブズは、高校時代に、コンピューターの基盤か何かのハードウェアを作る会社でアルバイトをしたりで、コンピューターハードは好きだったらしいが、1つの伝記によれば、ジョブスは、「現場のリーダーが出来る程度」のレベルだったとされる。
また、ジョブズは、リード大学を辞めた後、リード大学でカリグラフィ(文字装飾技術)の講座を熱心に聴いたらしいが、そのカリグラフィの知識が、後に、マッキントッシュコンピューターを作る際に役に立ったというから、一応これも専門と言えるかもしれない。
しかし、ジョブズもまた、実際には業界では素人程度の専門で始めていたのだ。こうした、ふたりのエマルジョン的反応が表の世界でジョブスを世界的成功者として導いているのだ。
また、マイクロソフト創業者の1人で、世界一の富豪ビル・ゲイツは、若い頃、「天才プログラマー」と言われていたが、彼は、自分のプログラマーとしての実績は「8080BASIC」という、初期のマイコン(パソコンの体をなさない簡易コンピューター)用のBASIC言語だけと言うが、その8080BASICも実際は、共同創業者のポール・アレンがほとんど作ったものらしい。
ビル・ゲイツもまた、プログラミングに関し、普通の人に比べれば人並み以上とされるが、やはり、業界では素人レベルと思っている人も多いそうなのだ。
こうしてビル・ゲイツは、ポール・アレンと言う共同創業者のポール・アレンとの「タッグ」を背景に世界一の富豪として成功している。
「こうして時間を掛けてきた物事だけが、現在において寄与される基盤があるとすれば、何も専門を持っている必要もなく、特別に超一流でなくても良いことが観てくる。」
こうした人の存在の背景には、チームやメンバーの「人」の「持ち味」をしっかり理解している、ただそれだけなのだろう。
個人の限界を知ることは、ほんとに成功に近づく合図なのかもしれいのだ。常に互いに限界を更新してくれるそんなパートナーとはビジネスにとって他者に無い強力な武器なのだろう。
それを解っておこなっているかどうかなのだろうか。常に「不可能」と「限界」が平常時のビジネス世界に「単なる人」の存在を重視する以上に強力な要素を占めているのだろう。
「頼る」ことが悪いことと思っている世界ほど、そのプラスの世界にも限界があることなのだろう。
「人」のカテゴリーをどう認識しているか、自身に影響を与えてくれる存在として認識しているか、また自身の為だけの「人」なのか。大きく影響される世界が変わるのだろう。
平常時からそのことが基本とすれば、まずは心底「頼りたい」と思えるだけ真剣に取り組んでみる。
「限界」にたどり着くまでいつも「本気」なのだろう。「本気」でなければ「限界」はいつまで経っても来ない、進歩しない壁が出来上がってしまうのだろう。
自身は早く「限界」を知りたいと思うだけに、いつも「本気」で取り組んでみる。そこにはセオリー織りなす体感時間など気にしない。 どこで何をしていても目標は「限界」に達すること。
「頼る」世界から更に飛躍していく世界もあることを信じているからなのだろう。
FXの世界もそういう世界なのだ。ステージごとに、チャレンジと改善、またチャレンジと改善をコツコツ繰り返しながらステップ・アップしていき、個人の限界を知るのだ。
「限界を知れることはチャンスなのだろう。」努力は当たり前と言ったものなのだ。
またたった2人の軸が揃ただけで、世界を塗り替えれるヒストリーが生まれるのだからロマンがあって面白いのだろう。
現在において、しっかり適材適所が行き届いた環境とは言えがたいとされるが、進捗や改革したい時ほど、お金では解決できない「人の価値に頼ってみる」のも、おもしろい経営なのだろうとふと思えるのだ。
頼り続ける経営論とかおもしろいとふと思うのだ。
にほんブログ村